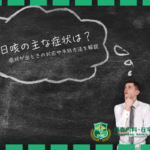マイコプラズマ肺炎はうつる?その期間や感染経路を解説
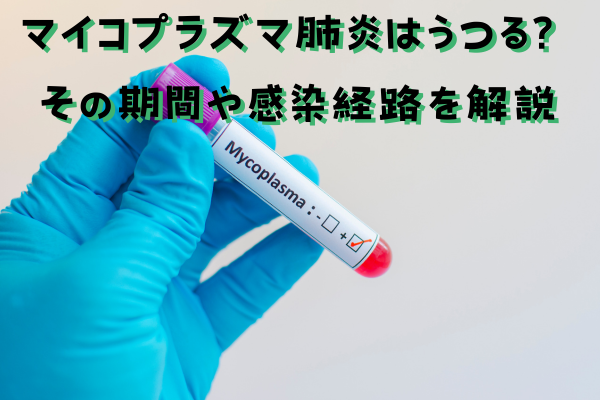
いきなりですが、皆様は「マイコプラズマ肺炎」という病気をご存じでしょうか?
マイコプラズマ肺炎は発熱と長引く咳が特徴の疾患です。
本記事では、マイコプラズマの潜伏期間やマイコプラズマ肺炎の感染経路、予防方法などについて詳しく解説していきます。
少し前から流行している病気なのでぜひ参考にして予防していきましょう。
目次
マイコプラズマとは?

気管支炎や肺炎を起こす細菌の一種です。
マイコプラズマは一般の細菌と異なり細胞壁をもたないため、効果のある抗菌薬も限られます。
こういった特徴からマイコプラズマによる肺炎は「非定型肺炎」と呼ばれます。
好発年齢
感染者の8割は子供で、特に5~12歳に流行しやすい感染症ですが、健康な大人でも感染することがあります。肺炎になる頻度
マイコプラズマに感染した場合の多くは軽症で、1週間程度で治癒していくため、いわゆる風邪と区別がつきません。しかし肺炎や気管支炎を引き起こすと、症状が長く続くことがあります。
マイコプラズマ感染によって肺炎になる方は、マイコプラズマ感染症全体の5%程度と言われています。
マイコプラズマ肺炎の症状の特徴
マイコプラズマ肺炎は、発熱と長引く強い咳が特徴です。
はじめは痰の絡まない乾いた咳から始まり、その後徐々に痰を伴いながら強くなり、3~4週間としつこく頑固な咳が続きます。
また一般的な細菌性肺炎と異なり肺炎にしては全身状態も悪くないことが特徴です。
関連記事:マイコプラズマ肺炎の咳が止まらないときの対処法|治療や予防方法について解説
マイコプラズマ肺炎の潜伏期間は?

マイコプラズマの潜伏期間は約2週間と長いことが知られています。
また発症約1週間前〜発症後6週間以上にわたり人にうつる可能性があり、人にうつる期間が非常に長いのがマイコプラズマの特徴です。
潜伏期間でも人にうつることがあるため、発症した地点で他の人にうつしている可能性もありますが、一番うつりやすいのは発症から約1週間と言われています。
感染のリスクを少しでも減らせるよう、マイコプラズマ流行期に発熱や咳があれば早めにマスク着用や手指消毒を行いましょう。

マイコプラズマ肺炎の感染経路

マイコプラズマのおもな感染経路は飛沫感染と接触感染です。
飛沫感染(ひまつかんせん)
感染者の唾液やくしゃみに含まれる飛沫を鼻や口から吸い込むことでうつることを言います。接触感染(せっしょくかんせん)
感染者の唾液や鼻水のついた物を手で触り、その手で自分の鼻や目をさわることでうつることを言います。
マイコプラズマ肺炎の予防方法

マイコプラズマはインフルエンザや新型コロナと比べると、比較的うつりにくい感染症です。
とはいえ、長時間一緒に過ごす家族や、保育園や学校ではうつる確率が非常に高いです。
しっかりと予防をすることで感染を防ぎましょう。
手洗い・うがい
感染予防の基本は手洗い・うがいです。手洗いは、流れる水で、石けんをつけて、よく泡立ててこすることがポイントです。
爪の間や指の間は十分に洗えていないことがあるので入念に洗いましょう。
また手洗いの後にアルコールなどの手指消毒薬を使用すると非常に効果的です。
うがいは、まずは「ブクブク」うがいで、口の中をきれいにし、続いて「ガラガラ」うがいでのどの奥のウイルスやほこりを取り除きます。
マスク着用
マスク着用は自身の感染を予防するだけでなく、周囲に感染を広げないためにも有効な予防法です。マスクの種類は布マスクより不織布マスクの方が感染予防効果が高いとされます。
着用に際してはプリーツを伸ばし鼻の上からあごの下までしっかりカバーすること、外す際には汚染面に触れないように紐の部分をもって外すことが感染を防ぐためのポイントとなります。
感染者との濃厚接触を避ける
家庭内での感染を避けるためにいわゆる3密の回避が基本です。
また以下も濃厚接触を避けるポイントとなります。
- マスクなしでの会話
- 換気のできていない部屋での接触
- 長時間の車同乗
- 会話をしながらの飲食
- 電話やパソコンの消毒
- タオルなどの共用を避ける
マイコプラズマ肺炎の治療方法

マイコプラズマ肺炎では基本的に抗菌薬による治療を行います。
効果のある抗菌薬
マクロライド系抗菌薬が一般に有効であり第一選択です。
ただし近年は抗菌薬の乱用の結果、小児を中心にマクロライド系抗菌薬に耐性のあるマイコプラズマによる感染も増えています。
マクロライド系抗菌薬を使用しても解熱しないケースでは、耐性菌による感染を疑い、ニューキノロン系やテトラサイクリン系の抗菌薬を使用することがあります。
必ずしも抗菌薬は必要ない
とある研究では、マイコプラズマ肺炎に効果の見込めない抗菌薬でも7割程度が改善・治癒したという報告もあり、抗菌薬を使用せずとも自然に熱が下がり軽快することも少なくないと考えられます。
このため受診時点ですでに熱が下がり咳だけ残っているようなケースでは、抗菌薬の有効性は限定的である可能性があります。
抗菌薬の使用には、稀ですが致死的なリスクもあるため、その適用には慎重な判断が必要と考えられます。
西春内科・在宅クリニックでできること
当院ではマイコプラズマ感染を含めて、発熱外来や内科診療を行っています。
マイコプラズマ感染は、臨床的には診断が難しいことが多々あります。
初期には風邪との見分けがほとんどつかず、迅速検査もありますが精度が低いため、迅速検査が陰性でもマイコプラズマ感染を否定できるものではありません。
当院ではレントゲンやCTでの精密検査による診断に基づいて、適切な診断による治療を心がけております。
まとめ
マイコプラズマ肺炎の概要をご紹介しました。
マイコプラズマ肺炎は発熱や頑固な咳を引き起こすことがあり、特に家庭内や小児で感染リスクが高まるため、予防と早期対応が非常に重要です。
手洗い・うがい、マスクの着用など基本的な予防策を徹底することで、感染リスクを最小限に抑えることができます。
もしもマイコプラズマ肺炎が疑われる症状が見られた場合には、早期に医療機関を受診し、適切な治療を受けることが最善の対応です。
マイコプラズマ肺炎について正しい知識を持ち、予防策を実践することで、自分自身や家族、そして周囲の人々を守ることができるでしょう。
監修医師: 西春内科・在宅クリニック 院長 島原 立樹

▶︎詳しいプロフィールはこちらを参照してください。
経歴
名古屋市立大学 医学部 医学科 卒業三重県立志摩病院
総合病院水戸協同病院 総合診療科
公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科