百日咳の主な症状は?症状が出ときの対応や予防方法を解説
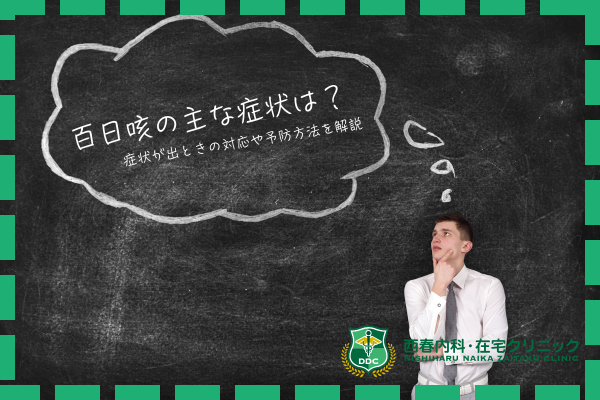
百日咳は、特に乳幼児や高齢者で重症化しやすい細菌性の感染症です。
この病気の名前の由来は、「百日間咳が続く」という特徴からきています。
激しい咳が長期間にわたって続き、日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、場合によっては命に関わる合併症を引き起こすこともあります。
本記事では、百日咳の主な症状や風邪との違い、症状が出た際の対応方法、そして予防方法について詳しく解説します。
百日咳とは?

百日咳とは、ボルデテラ・パーツシス(百日咳菌)という細菌によって引き起こされる感染症です。
ボルデテラ・パーツシス菌が鼻や喉から体内に侵入することにより感染。
この細菌は強力な毒素(百日咳毒素)を産生し、これが気道や肺の粘膜に炎症を起こして激しい咳を引き起こします。
毒素は気道の細胞や免疫細胞の働きを妨げるため、咳が長期間続き気道の回復が遅れる特徴もあります。
また、発症してしまうと激しい咳が1~3か月の間、続くことから「百日咳」と名付けられました。
百日咳は、飛沫感染を通じて広がるため、家庭や学校など、集団生活の場での感染予防が特に重要です。
また、ワクチン接種は百日咳の予防に非常に効果的とされており、幼少期に適切に接種することで重症化のリスクを大幅に低減することができます。
関連記事:咳止め市販薬おすすめランキング|選び方や服用の注意点などを解説
百日咳の主な症状

百日咳は、発症から回復までの症状が数週間にわたって段階的に変化することが特徴です。
特に「発作的な咳」が目立つ一方で、症状が進行するにつれてさまざまな健康上のリスクを伴うこともあります。
ここでは、百日咳の主な症状とそれぞれの段階でみられる特徴について詳しく解説していきます。
咳の特徴と期間
百日咳の主な症状は「激しい咳」で、通常の風邪やインフルエンザと異なり特定の特徴があります。
初期(カタル期)
風邪に似た症状が現れ軽い咳やくしゃみが1~2週間ほど続きます。
この段階では百日咳だと診断されにくく、他人への感染力が最も高い時期でもあります。
痙攣期
強い咳発作が繰り返されるピークの時期です。
しばしば呼吸困難を引き起こすため、特に幼児や高齢者にとっては大きなリスクを伴います。
通常2~3週間続きます。
回復期
発症から1か月以上経過すると、咳発作が減少し始める「回復期」に入ります。
完全に治るまでには数週間を要することもあります。
風邪・インフルエンザとの違い
百日咳が激しい咳が長く続くことがお分かりいただけたと思います。
しかし、風邪やインフルエンザであっても咳の症状が出ることがあるでしょう。
では、百日咳と風邪・インフルエンザにはどのような違いがあるのでしょうか。
下記の表に違いをまとめました。
百日咳 | 風邪・インフルエンザ | |
咳の期間 | 3週間以上 | 数日~1週間 |
発熱の有無 | 発熱がほとんどない | 発熱を伴うことが多い |
咳の強さ | 強い咳を繰り返す | 比較的軽度 |
百日咳の症状が出たときの対応

百日咳が疑われる症状が現れた場合、適切な対応が早期回復や症状の悪化防止に重要です。
百日咳の初期症状は風邪やインフルエンザに似ているため見過ごされやすい一方、早期の治療で重症化リスクを軽減できるため早めの対応が推奨されます。
ここでは、百日咳の疑いがある際の具体的な対応について解説します。
病院を受診するタイミング
百日咳が疑われる場合は、以下のような症状が見られた時点で早めに病院を受診することが重要です。
特に幼児や高齢者、基礎疾患のある人は、重症化しやすい傾向にあるため症状が軽度であっても早期に医療機関にかかることを推奨します。
発作的で強い咳が2週間以上続く場合
初期段階の風邪に似た咳が2週間以上続き次第に激しくなっている場合は、百日咳の可能性があります。
呼吸困難や「ひゅー」という呼吸音を伴う咳
咳発作の後に「ひゅー」という吸気音が聞こえる場合は百日咳の特徴的な症状です。
この音は、呼吸を大きく吸い込む際に狭くなった気道を通るために生じる音で、咳がひどく呼吸が苦しい証拠です。
咳による嘔吐や顔色の変化
咳が続くことで顔が赤くなったり嘔吐を伴ったりする場合は、強い咳によって気道が狭くなっている状態です。
このような症状が見られる場合も受診が必要です。
乳幼児や高齢者、妊婦の感染
体力が低下している乳幼児や高齢者、妊婦で重症化しやすいため、これらの人に百日咳の症状がみられた場合は早めの診察が必要です。
治療方法
百日咳は細菌感染によるため、治療には主に抗生物質が使用されます。
また、重症度や患者の年齢、持病の有無に応じて治療の方法や入院が検討されることもあります。
抗生物質の投与
百日咳の治療の第一選択は、細菌を除去するための抗生物質です。
通常、マクロライド系抗生物質(エリスロマイシンやクラリスロマイシンなど)が用いられます。
効果
抗生物質の使用は、百日咳の原因菌であるボルデテラ・パータシス菌の増殖を抑制します。
特に発症から2週間以内の早期に抗生物質を投与することで、症状の重症化や感染期間の短縮が期待できます。
発症後の抗生物質の有効性
発症から2週間以上経過した場合、すでに痙攣期に入っていることが多く、抗生物質の効果は限定的ですが、感染力を抑制し、周囲への二次感染を防ぐためにも重要です。
咳を抑える対症療法
激しい咳が長期にわたって続くため、対症療法として咳止め薬や鎮静剤が処方されることもあります。
ただし、百日咳に対しては一般的な咳止めが効果を発揮しないケースが多いため、無理に咳を止めるよりも、気道の潤いを保つことが推奨されます。
加湿
部屋の湿度を保ち、加湿器や蒸しタオルなどを使用することで、乾燥からくる気道の刺激を緩和し、咳を軽減するのに役立ちます。
体位の調整
夜間に咳が悪化する場合は、寝る際に上半身を少し高くして気道の圧迫を軽減する方法もあります。
特に乳幼児では、ベッドや枕の調整が有効です。
重症例や乳幼児の場合の入院治療
症状が重篤である場合や乳幼児の場合、入院治療が勧められることがあります。
特に呼吸困難や窒息のリスクがある場合には酸素投与や点滴治療が必要です。
酸素投与
呼吸が苦しい場合には酸素を供給し、呼吸を楽にする処置が行われます。
酸素投与により、気道への負担が軽減されます。
点滴治療
嘔吐が頻発する場合や食事が取れない場合には、点滴で水分や栄養を補うことがあります。
特に乳幼児では脱水症状の予防が重要です。
関連記事:RSウイルスに高齢者が感染すると危険?重症化や死亡のリスクについても
百日咳の合併症
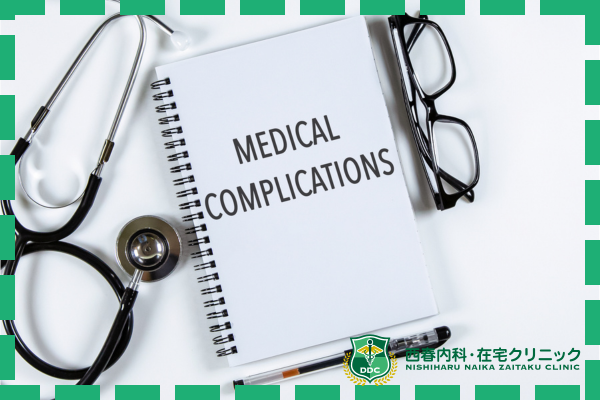
百日咳は、特に幼児や高齢者においては合併症を引き起こすリスクがあります。
ここでは代表的な合併症について解説します。
呼吸不全・窒息
百日咳の主症状である激しい咳発作は、気道や呼吸器系に大きな負担を与えます。
特に乳幼児では気道が狭く、百日咳の激しい咳により気道が閉塞し窒息するリスクがあります。
呼吸不全
咳発作が続くと、肺や横隔膜に大きな負担がかかり、正常な呼吸が困難になります。
特に幼児では、肺が未熟であるために呼吸不全に陥る可能性が高く、酸素投与が必要になることもあります。
窒息のリスク
咳が発作的に連続して出ることで気道が一時的に閉塞し、窒息のリスクが高まります。
呼吸が苦しそうな様子が見られる場合はすぐに医療機関での対応が必要です。
脳出血
百日咳の強い咳発作は、体内の血圧を一時的に上昇させます。
特に小児や高齢者では血管が弱いため強い咳が続くと血管に負担がかかり、稀に脳出血を引き起こすことがあります。
脳内の血管に圧力がかかる
激しい咳の繰り返しによって血圧が急激に上がり、脳内の細い血管が破れることがあります。
脳出血を起こすと、嘔吐、意識障害、けいれんといった症状が現れるため、これらの症状が見られた場合は速やかに医療機関を受診することが重要です。
中耳炎
百日咳の激しい咳や鼻水が続くと、耳と鼻をつなぐ耳管に炎症が起こりやすくなります。
そのため、百日咳の合併症として中耳炎が発生するケースもあります。
耳管の炎症
咳発作や鼻水が耳管に流れ込みやすくなり、細菌が侵入して中耳炎を引き起こすことがあります。
中耳炎が起こると耳の痛みや聞こえにくさが見られ、さらに細菌感染が広がると、鼓膜に膿がたまるなどの症状に発展することもあります。
特に乳幼児で発生しやすい
耳管が短くて水平に近い乳幼児は、中耳炎が発生しやすいため注意が必要です。
気管支肺炎
百日咳にかかった後、細菌感染が合併し気管支や肺に広がり気管支炎や肺炎を引き起こすことがあります。
気管支肺炎は重症化しやすく、適切な治療が行われなければ命に関わることもあるため注意が必要です。
気道への細菌感染
百日咳の咳が続くと気道が炎症を起こし、そこに細菌が入り込むことで気管支や肺に感染が広がります。
症状
発熱や息切れ、胸痛、呼吸困難などの症状が見られ、特に体力の弱い乳幼児や高齢者に多く発生します。
肺炎による呼吸困難
肺炎が重症化すると呼吸機能が低下し、酸素不足になるため、酸素投与や点滴などが必要です。
気胸
激しい咳発作が続くことで、肺に強い圧力がかかり、肺の一部が破れる「気胸」という状態になることもあります。
気胸は自然に治ることもありますが、重度の場合は緊急処置が必要です。
気胸の発生メカニズム
強い咳によって肺の内部に圧力がかかり、肺の一部が破れて空気が漏れると気胸が発生します。
気胸の症状
呼吸困難や胸の痛みが突然現れ、息を吸うと痛みが増すことが多いです。
軽度の気胸は自然に治癒することもありますが、重度の場合は肺の圧力を抜くための処置が必要になります。
脱腸(鼠径ヘルニア)
激しい咳発作が続くと、腹部に圧力がかかり、「脱腸(鼠径ヘルニア)」を引き起こすことがあります。
特に小児では腹部の筋肉が発達していないため、脱腸が発生しやすい状態です。
鼠径ヘルニアの原因
咳が続くことで腹圧がかかり、腸の一部が鼠径部(股の付け根部分)に押し出されてしまうことで発生します。
脱腸が起こると、鼠径部に膨らみが見られるようになります。
鼠径ヘルニアの症状
鼠径部が腫れる、痛みが出る場合があります。
通常は自然に戻ることもありますが、戻らない場合は外科的処置が必要です。
百日咳の予防方法

百日咳は感染力が強く、家庭や保育園・幼稚園、学校、職場などで感染拡大が問題となる場合もあります。
ここでは予防方法について解説します。
ワクチン接種
百日咳の予防で最も効果的な方法はワクチン接種です。
ワクチンによる免疫を得ることで感染を防ぎ、また感染したとしても重症化を防ぐ効果が期待できます。
日本では「三種混合ワクチン(DPT)」または「四種混合ワクチン(DPT-IPV)」が、乳幼児期に定期接種として行われています。
DPTワクチン
DPTはジフテリア(Diphtheria)、百日咳(Pertussis)、破傷風(Tetanus)の三種混合ワクチンで、乳幼児が百日咳を含む重篤な感染症に対する免疫を得るために接種します。
DPT-IPVワクチン
DPTにポリオ(Poliovirus)の予防効果が追加された四種混合ワクチンです。
現在日本では四種混合ワクチンが主流となっており、定期接種に組み込まれています。
手洗い・うがい
百日咳は飛沫感染によって広がるため、日常的な感染対策として「手洗い」や「うがい」を徹底することが大切です。
特に外出後や人が多く集まる場所から帰宅した際には、手洗い・うがいを習慣づけましょう。
手洗いのポイント
手洗いの際には石鹸を使い、手のひらや指の間、爪の間などを念入りに洗います。
洗い残しがないように約30秒ほどかけてしっかりと洗い、流水で十分にすすいだ後は清潔なタオルやペーパータオルで拭き取ります。
うがいの効果
うがいによって喉や気道に付着した細菌やウイルスを洗い流すことができます。
うがい薬を使用することも有効ですが、単に水でうがいするだけでも効果が期待できます。
マスク着用や咳エチケットの実践
百日咳は飛沫感染によって周囲に拡散しやすいため、「マスクの着用」や「咳エチケット」を守ることで他者への感染を予防することができます。
マスクの着用
百日咳が疑われる場合や流行している地域では、マスクを着用することで飛沫の拡散を防ぐことができます。
特に乳幼児や高齢者と接する際には、感染予防のためにマスクを着用することが推奨されます。
咳エチケットの実践
咳やくしゃみをする際は、口元をティッシュや肘で覆うようにして、飛沫の飛散を防ぎます。
使ったティッシュはすぐに処分し、その後は手を洗うことで、周囲への二次感染を防止します。
関連記事:マイコプラズマ肺炎の咳が止まらないときの対処法|治療や予防方法について解説
西春内科・在宅クリニックでできること
当院では長引く咳の患者様の診療を多く行っております。
長引く咳には百日咳以外にも、肺炎、マイコプラズマ感染、気管支喘息、咳喘息、アトピー咳嗽、後鼻漏、逆流性食道炎などさまざまな原因があります。
上記の疾患を鑑別するためには胸部レントゲン検査やCT検査が必要になることも多くあります。
当院はCTを完備しておりますので、精密な検査が可能となっております。
長引く咳に対して原因を突き止めることなく漫然と咳止め薬など使用しても改善しないケースがありますので、当院では適切な診断に基づいた治療を心がけております。
まとめ
百日咳は重篤な症状を引き起こすことがあり、特に幼児や高齢者では合併症のリスクが高まるため、予防と早期対応が非常に重要です。
ワクチン接種、手洗い・うがい、マスクの着用など基本的な予防策を徹底することで、感染リスクを最小限に抑えることができます。
もしも百日咳が疑われる症状が見られた場合には、早期に医療機関を受診し、適切な治療を受けることが最善の対応です。
百日咳について正しい知識を持ち、予防策を実践することで、自分自身や家族、そして周囲の人々を守ることができるでしょう。
参考文献
百日咳とはどんな病気?感染しない・広げないためにすべきこと | 横浜弘明寺呼吸器内科クリニック
ノロウイルス|予防法|原因と経路|食中毒|便|嘔吐物
百日咳【医師監修】特徴的な症状は長く続く激しい咳 ワクチン接種で予防を! 大人に流行することも | 病院なび
百日咳|くにちか内科クリニック
監修医師: 西春内科・在宅クリニック 院長 島原 立樹

▶︎詳しいプロフィールはこちらを参照してください。
経歴
名古屋市立大学 医学部 医学科 卒業三重県立志摩病院
総合病院水戸協同病院 総合診療科
公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科



