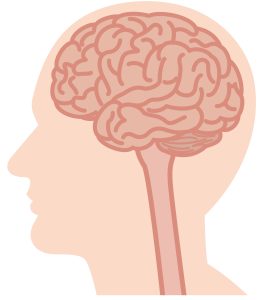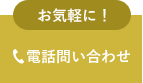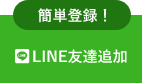認知症が一気に進む原因とは?入院すると急激に悪化する?
以下皆さん、認知症について深く考えたことはありますか?
認知症は予防法をうまく生活に取り入れておくと、万が一認知症になった後でも、症状の進行がゆるやかになり、生活の質を保つことができます。
いつまでもはつらつとした生活を送りたいですよね。
そこで今回は認知症が一気に進む原因や日頃からできる予防、対策法などについて詳しく解説します。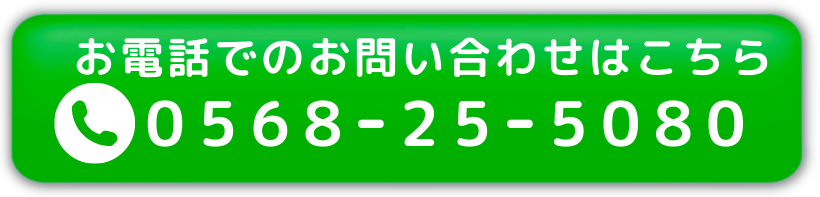
目次
認知症が一気に進むかもしれない原因

認知症の進行速度は人によって大きく異なります。先ほど紹介した認知症の種類や個人個人の遺伝的要因ももちろん絡みますが、生活スタイルでも進行速度が変わる場合があります。
ここでは、認知症が一気に進む原因について確認しておきましょう。
早期に発見できなかった
まずはなんといっても早期に発見できたかが非常に重要です。
認知症の発症初期は緩やかに進行しても、ある時点から急激に症状が重くなることもあります。
かなり進行してしまってから実は認知症だったとわかるケースでは、発覚して間もなく症状が一気に進むといったこともありえます。
早期発見には本人よりも周りの人が気付てあげることが効果的です。身近な人が「最近物忘れがひどいな」と感じたら、物忘れ外来などの病院を受診することを勧めてあげましょう。
どこを受診すればいいかわからない場合は、各地区の地域包括支援センターに連絡をすれば適切な医療機関を紹介してもらえます。
脳への刺激が少ない
脳の細胞は何らかの刺激を受けることで活性化し、使わなければその機能はみるみるうちに低下していきます。
日々刺激的なこともなく、脳の機能を使わない生活を続けてしまうと脳が委縮し、結果として認知症の進行を早めることに繋がるでしょう。
独居の高齢者が外出する機会が極端に減ったり寝たきりの生活が続き、認知症を発症してから誰にも気付かれずに進行してしまっていたというケースがよく見られます。
強いストレス
過度なストレスが認知症の進行に悪影響を及ぼす場合もあります。ストレスを受けたときに分泌されるコルチゾールというホルモンは、適量であれば様々なメリットがありますが、分泌されすぎると記憶力の低下などといった副作用があり、認知症を進行させる恐れがあるとされています。
また、他人からの過度な責によって無気力状態になってしまうと活動量が減り、認知症の進行を早める結果に繋がることも。
さらには病気や怪我による入院、施設への入居、身近な人の死といった急激な環境の変化でも強いストレスを感じ、認知症が一気に進行した例が報告されています。
認知症の進行を遅らせるためには脳への適度な刺激が必要ですが、過度な刺激はストレスとなって認知症を悪化させてしまう恐れがあることを覚えておきましょう。
認知症の種類と特徴
世間では「認知症」と一括りにされていますが、大きく分けて下記の4種類に分類されています。
- アルツハイマー型
- レビー小体型
- 脳血管型
- 前頭側頭型
それぞれ原因や症状の現れ方が異なるため、初期の兆候を見逃さないためにも、認知症の各種類について確認しておきましょう。
アルツハイマー型
認知症の中で最もメジャーな型で、「アルツハイマー病」と呼ばれているのは、実はアルツハイマー型の認知症のことです。
アルツハイマー型認知症は脳にアミロイドβというたんぱく質が蓄積することと、神経線維が変性してしまうのが特徴です。
初期に見られる症状としては、
- 数分~数時間前など、ごく短期間のことを忘れる
- よく使う言葉なのにとっさに出ない
- 親しみのある人や物の名前が出てこない
- 大切なものをよく失くす
- 好きだったことに急に興味を示さなくなる
といったものが挙げられます。いわゆる認知症の特徴に当てはまれば、まずはアルツハイマー型を疑うとよいでしょう。
レビー小体型
レビー小体型認知症は、認知機能が正常なときとそうでないときの波が激しいのが特徴です。高齢者になると認知症でなくても物忘れが多くなってくるので、認知症を疑われにくいのが厄介な点といえるでしょう。
しかし他の認知症と決定的に違う点があり、
- 幻視
- パーキンソン症状
- 睡眠中の異常行動
- ネガティブすぎる言動
- めまいや立ちくらみ
上記のような症状が見られやすいことです。
実際にはないものが見えていると発言したり、動作が緩慢になったり小刻みに震える様子が見られた場合にはレビー小体型を疑いましょう。
脳血管型
脳梗塞や脳出血によって脳の一部に十分な血液が供給されなくなり、その結果脳の一部の機能が低下して認知機能に影響を及ぼします。
認知機能に関する症状はアルツハイマー型とよく似ていますが、脳卒中の前後で明らかに認知機能の低下が見られる場合は脳血管型であることが濃厚です。
前頭側頭型
文字通り社会性や倫理観を司る前頭葉、知識や記憶を司る側頭葉に何らかの障害が起こることで発症する認知症。
- 社会性の欠落(万引き、信号無視など)
- 性格が暴力的になる
- 自分や他人に無関心になる
- 同じ行動を繰り返す
上記のような症状が見られるようになります。一方で認知機能の低下はあまり目立たないことも。
そのため認知症ではなく他の精神疾患などと診断されることも少なくない病気です。
認知症になりやすい人の特徴

認知症については数々の研究が世界中で行われており、認知症になりやすい人の特徴はかなりわかってきています。
まずは年齢ですが、言うまでもなく歳を取るほど認知症になりやすくなります。
これはイメージしやすいと思いますが、とはいえ歳をとるとみんなが認知症になるわけではありません。
そこで2017年にLancetと呼ばれる学術雑誌に掲載された認知症のリスク因子に関わる研究を紹介します。
それによると、認知症になりやすい 人の特徴との言える認知症のリスク因子としての以下の12個が挙げられました。
|
上記のうち、特に高血圧や糖尿病は肥満や喫煙、運動不足、アルコールの過剰摂取は、いわゆる生活習慣病とも言われます。生活習慣病をもっていると、それだけ認知症になるリスクが高いと示唆されているのです。
これらの12個の因子には修正可能なものもあるため、当てはまる人は積極的に改善していく必要があります。
これらの因子に当てはめると、実に全世界の認知症患者の40%がこれに当てはまります。要するに認知症になりやすい 人の特徴とも言えます。
理論的には上記12個の因子を修正すれば認知症の発生リスクを40%も軽減し、また発症したとしても発症時期を遅らせる可能性があります。これは我々現場の医師からすればとてつもない効果です。
また、社会的孤立という因子は、さらに詳しくみると性格と深く関わっています。
どのような人が社会的孤立をしやすいかというと、気が短くてイライラしやすい性格の人は時間とともに人との関わり合いが減ってきて最終的に孤立する可能性が高くなります。
他人との協調性が低い人も孤立しやすいため注意が必要です。また他にもマイナス思考でネガティブな口癖をもっているような人はうつ病を発生しやすいので、結果的に認知症のリスクが高いといえます。
「自分に当てはまっているな」と思った方は、将来認知症にならないためにも少し改善が必要かもしれません。
Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30367-6/fulltext
認知症は入院すると急激に悪化する?
医療の現場でしばしば見られるケースとして、認知症のある人が認知症以外の原因で入院・治療し、入院中や入院後に認知症が一気に進むことがあります。
これは入院することでベッド上での生活を余儀なくされた結果、食事の用意や洗濯・掃除などの日常生活を一時的にしなくなり、生活にハリがなくなって脳への刺激が減ったことで認知症が一気に進行したと考えられています。
生活環境の変化に人は非常に敏感です。
認知症になる前から万病の元である高血圧や糖尿病、肥満などを予防し入院する必要がないようにするのが理想です。また認知症になってからは、より一層入院しなくて済むような健康管理が重要となるでしょう。
認知症の症状について
認知症の症状は大きく分けて中核症状と行動・心理症状があります。具体的に見ていきましょう。
中核症状
中核症状とは認知症の症状の中心であり、記憶障害や見当識障害が挙げられます。
記憶障害
記憶障害は認知症の症状として最も有名です。
しかし単なる物忘れなのか、問題のある物忘れなのかの判断は意外と難しいと思います。
少しでもおかしいと思ったらすぐに上記のような専門施設に相談して欲しいですが、一つの目安を紹介します。
患者さんでもよく「最近物忘れがひどくて、昨日食べたご飯がなんだったがすぐ思い出せないんです、私って認知症なんでしょうか?」と心配されている方がおられます。
ただ知っておいて欲しいのは、人間は忘れる生き物です。それは普通のことです。
しかし昼ごはんを「食べた」という事実自体を忘れてもう一度ご飯を食べるというのは問題のある物忘れです。
他にも初めて会った人の名前をすぐ忘れたというのは割とあることですが、昔から知っている友人の名前が出てこないのも問題のある物忘れです。
これを専門用語でいうと短期記憶と長期記憶といい、短期記憶は忘れて当然なので普通のことですが、友人の名前や自分の電話番号などは長期記憶に分類され、これを忘れるのは問題があります。
これらの例を一つの目安にして、認知症の早期発見に役立ててください。
見当識障害
「見当識障害」は聞き慣れない言葉かもしれません。
見当識とは現在の日時や時刻、また今自分がどこにいるかなどの状況の把握のことを言います。
医療の現場では意識レベルの評価などに用います。認知症では、この見当識も障害されます。
認知症の方に今日の日付を聞くと、日にちを間違えるどころか月を間違えたり、季節を間違えたりすることもあります。
また場所もわからなくなるため普段住んでいる街で道に迷ったり、家に帰れなくなったりすることもあります。
以上のような障害の結果、様々な症状が出現します。
いくつか例を挙げましょう。
- 理解力が低下してお金の管理ができなくなる
- 運転がうまくできなくなる
- 今までできていた料理ができなくなったり、味付けなどがおかしくなる
- 家事の段取りができなくなったり、仕事の効率が落ちる
- 身だしなみが疎かになって季節にあった服を選べなくなる
我々人間は記憶や見当識といった能力を日常生活の中で無意識に使っており、これらが傷害されることにより様々な症状が引き起こされるということです。
行動・心理症状
行動や心理症状では、性格の変化が挙げられます。
例えば今まで熱心にやっていた趣味に興味を示さなくなったり、何をするのも面倒くさがったりします。
また、一人でいることを異常に怖がったり不安に思う一方で、些細なことで怒ったりイライラすることが多くなったりします。
また被害妄想が多くなり、自分のものが誰かに取られたと疑う「物取られ妄想」をいった症状が出現することもあります。
おそらくこれらは、認知症によって今まで生きてきて獲得した「我慢」など高度な脳機能がうまく働かなくなり、持って生まれた「気質」みないなものが前面に出てしまい、その結果上記のような様々な症状が出るのではないかと思います。
認知症の症状は、本当に人それぞれです。
>>アルツハイマーと認知症の違いは?原因や初期症状、なりやすい人の特徴について
日頃からできる認知症の予防と対策法
認知症の予防や対策法としてはすでに紹介した「修正可能な12個のリスク因子」である下記を改善する必要があります。
|
また、すでに認知症を発症している場合も同様です。1つずつ日頃からできる認知症の予防と対策法について見ていきましょう。
運動
運動は激しい運動よりも、散歩やジョギングといった有酸素運動が効果的です。
こういった有酸素運動は肥満の改善・予防に役立ちます。
また運動は思いつきで時々やるのではなく、日々できる程度の有酸素運動(頑張らなくてもいい程度)を毎日の習慣にすることが重要と考えます。
これらは認知症の予防だけでなく肥満の解消から高血圧や糖尿病、コレステロール異常などといった生活習慣病の改善にも効果的です。
どうしても「運動しなきゃ!」と思うと頑張りすぎて3日坊主になりがちですが、なんといっても重要なことは習慣化することです。まずはできる範囲で(5分くらいの散歩でも)十分なので、はじめてみましょう。
ここで一つ注意しなければいけない点があります。それは定期的な運動については、先述の「Lancet」の論文によると効果は患者の年齢によって異なるとされています。
一番効果的なのは中年の方と言われています。ちょうど生活習慣病が発症するくらいの年齢です。
それを過ぎて高齢者になりますとやや運動の重要度は下がります。
とはいっても運動がダメなわけではありませんので、自分のできる範囲の軽い運動を是非続けていただきたいと思います。
社会的孤立を防ぐ
認知症は社会や他者との関わりがなくなると発症しやすく、またすでに認知症の方は症状が早く進行します。
これは社会や他者と触れ合うことは、コミュニケーションなどの様々な脳の活動を無意識に行う必要があり、言うならば最高の「脳トレーニング」になるからです。
人間は社会性を持つ生き物です。趣味などがあるならぜひそれを大事にして、それを通じて社会との関わりを持ち続けましょう。
趣味がこれといってない方は、是非色々な知らない世界を覗いてみて、積極的に趣味を持ちましょう。
どうしてもそういったことができない場合は、指先を使ったような手遊び、例えば裁縫なども脳トレーニングになりますので検討してみてください。
生活習慣病を治す
上記の修正可能な12個のリスク因子の中に高血圧や糖尿病といった生活習慣病も入っています。
これらの病気は医師による適切な対応が必要ですが、ご自身でも食事や運動習慣の見直しが重要です。
生活習慣病は何か症状が出た時にはかなり進行しています。
普段からバランスの取れた食事を心がけ、運動習慣も持ち適正体重を維持するようにしましょう。
世の中では食事は様々なことが言われており、何がいいかはわかりにくいと思います。
医学的にも確実にこれがいいという食事は実はよくわかっていませんが、日本人にあった対応としては
- 野菜を積極的に撮る
- 外食はし過ぎないようにする(外食は塩分が多い傾向にあります)
- 魚や大豆製品を積極的に食べる(豚肉や牛肉、鶏肉といった動物性脂肪は取り過ぎないようにする)
- 夕食は和食中心にする(夕食は食べ過ぎず、夕食後は食べないようにする)
といったポイントが挙げられます。また喫煙や過度なアルコール摂取の習慣がある方は改善する必要があります。
会社の検診で生活習慣病の疑いがあると言われた場合は放置せず、医療機関を受診することをお勧めします。主婦の方などで会社の検診がない方は時々でも大丈夫なので地域の健康診断を受けてみましょう。
病気は全て、病気になってからの対応よりも早期発見と予防が最も重要です。
難聴を治す
難聴も認知症のリスク因子のひとつです。
難聴はいきなりなるとわかりやすいですが、徐々に進行すると本人は意外と気付かなかったりします。
難聴になると外界からの情報が脳に届きにくくなり、結果として認知症のリスクが高くなります。
検診で聴力の低下を認めた場合は早めに医師にかかるようにしましょう。
最近では様々なタイプの補聴器が出ており、これらの道具を使えば難聴も十分に修正可能です。
難聴も本人だけでなく周囲の人の気付きが重要です。最近聞き返しが多いなと感じたら放置せず、医療機関の受診を勧めてください。
>>物忘れがひどくなる原因は?|認知症との違いや物忘れ対策について
もし家族や身内が認知症になったときの対応

もし身近な人が認知症になった場合、その後の対応がこれまで以上に重要となります。
まずは修正可能な12個のリスク因子について当てはまるものを調べ、それぞれ可能なら医療施設なども受診しながら改善していくことが重要です。
また認知症を診察するための主治医、地域のかかりつけ医を見つけることも重要です。
認知症には進行を遅らせる飲み薬などもあります。
積極的に医学の力も使いながら、適切に対応しましょう。
西春内科在宅クリニックができる対応
当院では認知症・物忘れ外来を設置しております。
当院の医師による問診と心理検査など物忘れ・認知症に関する専門的な検査を受けることができます。
さらに詳しい検査が必要な場合には、頭部CTなど画像検査を使っての検査も行うことができます。
検査の結果を確認し、医師による総合的な診断が行われます。
まとめ
本記事を読んで、認知症についての理解が少しでも深まり、その結果自分や身近な人の役にたてば幸いです。
繰り返しになりますが認知症は予防と早期発見が非常に重要です。
そのためには修正可能な12個のリスク因子について、一つでも減らせるように少しずつ生活習慣を見直しましょう。
参考文献
(1) Gill Livingston, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet Journal. 2020 Aug 8;396(10248):413-446.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30367-6/fulltext
(2) Petros Stamatelos, et al. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2021;35:315-320.
https://pmc.carenet.com/?pmid=34654042
監修医師: 麻酔科 弓場 智雄

経歴
2014年 大阪大学卒業2014~2016年 国立病院機構呉医療センター
2016年 大阪大学心臓血管外科
2017年 大阪大学麻酔科集中治療部
2018年 国立成育医療研究センター麻酔科
2019年~大阪大学麻酔科集中治療部 医員