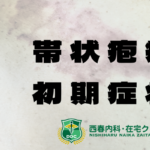カビアレルギーの主な症状と対策法|住環境と年齢による違いも解説
花粉の時期が終わったのに鼻水が長引く、咳やかゆみが続く、という症状がある場合、カビが原因となっている可能性があります。
自宅を含め、カビは私たちの生活環境に広く存在します。
カビに対してアレルギー反応を起こす人はしばしば見られ、年齢や体質によって症状の出方が異なります。
ここでは、カビアレルギーの症状や検査、生活でできる対策について解説します。
目次
カビアレルギーとは
カビアレルギーとは、カビが放出する胞子などを吸い込んだり、皮膚や粘膜に触れたりすることで、アレルギー症状を引き起こした状態です。
日本では高温多湿になりやすく、梅雨から夏にかけてはもちろん、冬場でも結露や暖房による湿気でカビが繁殖しやすくなります。
そのため一年を通じて発症の可能性があり、「花粉症が終わったのに鼻炎が続く」と感じる方は、カビアレルギーである可能性があります。
また、喘息・アトピー性皮膚炎を持つなどアレルギー体質の方は、カビにより症状が悪化することも少なくありません。
カビアレルギーの主な症状
| 生息場所 | 主なカビの種類 | 想定される症状 |
| 押し入れ・壁紙・浴室など | アスペルギルス、ペニシリウム | 鼻水・咳・喘息、皮膚のかゆみ、アトピー悪化 |
| エアコン・加湿器・空気清浄機内部 | クラドスポリウム、アスペルギルス | 喉の違和感、咳、気管支炎、呼吸困難感 |
| 食品(パン・果物・味噌など) | ペニシリウム、ムコール、リゾプス | 腹痛、体調不良、皮膚の湿疹 |
| 土壌・落ち葉・庭木など(屋外) | アルテルナリア、クラドスポリウム | 花粉症に似た症状(くしゃみ・鼻水・目のかゆみなど) |
| 収納された布団やカーテン | ペニシリウム、アスペルギルス | 鼻炎、咳、アトピー性皮膚炎の悪化 |
年齢によって以下のように出やすい症状が異なります。
- 子ども:気管支が敏感で喘息や鼻炎が出やすい
- 成人:皮膚炎やアトピーの悪化
- 高齢者:免疫力が低下し、過敏性肺炎など重症化することがある
関連記事:アトピー咳嗽の原因はストレス?症状のチェック項目や治し方を紹介
関連記事:小児のアトピー性皮膚炎の原因は?年代別の特徴を解説
カビアレルギーの検査方法
カビによるアレルギー症状が疑われる場合、病院ではいくつかの検査を組み合わせて診断します。
主な方法は以下の通りです。
血液検査
採血を行い、血液中に「カビに対する特異的IgE抗体」があるかどうかを調べます。
アスペルギルスやクラドスポリウムなど複数のカビに反応を確認できるため、代表的でよく行われる検査です。
結果は数日で判明し、保険が適用されることが多いです。
向いている人:子どもや皮膚が弱い人、複数のアレルギーの有無をまとめて調べたい人。
皮膚プリックテスト
腕や背中の皮膚にごく少量のカビ抗原を滴下し、針で軽く刺激を与える検査です。
15〜20分程度でアレルギー反応の有無が分かります。
即時型アレルギーの診断に有効で、食物アレルギーでも用いられます。
向いている人:鼻炎や喘息など、アレルギー症状が季節性・環境性に強く出る人。ただし、皮膚症状がひどい場合や乳幼児には不向きなことがあります。
パッチテスト
背中などにカビ抗原を浸したシートを貼り、48時間後に皮膚の反応を確認する検査です。
接触皮膚炎などの遅延型アレルギーを調べる際に有効で、皮膚症状が強い方に用いられます。
向いている人:アトピー性皮膚炎が悪化する人や、特定の住環境で湿疹・かぶれが強くなる人。
検査費用と保険適用の有無
血液検査やプリックテストは保険が適用されるケースが多く、自己負担は数千円程度です。
パッチテストは検査内容によっては保険適用外になる場合もあるため、事前に医療機関へ確認が必要です。
病院を受診すべきタイミングと診療科の選び方
カビアレルギーは、軽い鼻水や咳などで済むこともありますが、重症化すると生活に大きな支障をきたします。
以下のような場合は、自己判断せずに早めの受診が望まれます。
受診を検討すべき症状の目安
- 市販薬や掃除・換気の工夫をしても鼻炎や咳が長引く
- 季節や天候に関係なく、家の中で症状が悪化する
- 喘息のようなゼーゼーした呼吸や息苦しさがある
- アトピー性皮膚炎や湿疹が住環境によって悪化する
- 子どもが夜間の咳や鼻づまりで眠れない
こうした症状がある場合は、病状が悪化する前に、早めに受診することが重要です。
受診する診療科の選び方
- 耳鼻咽喉科:鼻炎・副鼻腔炎・喉の違和感が中心の方
- 呼吸器内科:咳・喘息症状・息苦しさがある方
- 皮膚科:湿疹やアトピー性皮膚炎の悪化が見られる方
- 小児科:子どもの咳・鼻炎・皮膚症状が続く場合
また、複数の症状が重なっている場合は、アレルギー科のある医療機関を受診すると、総合的に検査・治療を受けやすいです。
日常生活でできるカビアレルギー対策
カビアレルギーの症状を軽減するためには、住環境からカビを減らす工夫が欠かせません。
以下の方法を日常生活に取り入れることで、症状の予防や悪化防止につながります。
湿度管理・換気
室内の湿度は50〜60%以下を目安に調整するようにしましょう。
除湿機やエアコンの除湿機能を活用することで湿度管理をしやすくなります。
入浴後や料理後は窓を開けたり、換気扇を回すなどで湿気を逃がすことも効果的です。
エアコンの定期洗浄
エアコンのフィルターや内部にカビが繁殖しやすいため、2週間に1回程度の掃除がおすすめです。
また、専門業者による内部洗浄を年1回ほど行うことで、カビを除去することができます。
空気清浄機の活用
HEPAフィルター搭載の空気清浄機を使用すると、カビの胞子を効率的に除去することが可能です。
空気清浄機も定期的にフィルターを交換し、性能を維持するようにしましょう。
こまめな掃除
浴室、押し入れ、窓際など湿気がこもる場所を重点的に掃除しましょう。
除機だけでなく、拭き掃除を取り入れると効果的です。
拭き掃除の際に漂白剤やアルコールを使用することでカビの再発防止につながります。
寝具の清潔を維持
布団やシーツは週1回の洗濯、布団乾燥機や天日干しで乾燥させましょう。
押し入れ収納時は除湿剤を併用するとカビの温床となる湿気が溜まるのを予防できます。
カビの除去・消毒
すでに発生したカビは、塩素系漂白剤やアルコールで除去が可能です。
壁や天井など広範囲にカビが発生している場合は、専門業者に依頼することも検討しましょう。
関連記事:アレルギー薬に強さの違いはある?タイプ別おすすめ市販薬ランキング
関連記事:喘息治療に使う吸入薬とは?長期管理・発作治療に分けておすすめ吸入薬紹介
西春内科・在宅クリニックでできる対応
当院は内科の他にアレルギー科を標榜しおり、血液検査(特異的IgE抗体測定)が可能です。
どのカビに反応しているかを確認し、症状の原因を特定します。
症状に応じて、抗アレルギー薬や吸入薬、点鼻薬の処方を行っています。
自宅でできるカビ対策、掃除や湿度管理の工夫についてのアドバイスも可能なため、カビアレルギーの方や疑いのある方はお気軽にご相談下さい。
まとめ
今回はカビアレルギーについて解説しました。
カビアレルギーは鼻炎や咳、喘息、皮膚症状など多彩な症状を引き起こし、生活の質を大きく低下させる原因となります。
症状が続く、あるいは悪化する場合は自己判断せず、医療機関へ早めに相談しましょう。
監修医師: 西春内科・在宅クリニック 院長 島原 立樹

▶︎詳しいプロフィールはこちらを参照してください。
経歴
名古屋市立大学 医学部 医学科 卒業三重県立志摩病院
総合病院水戸協同病院 総合診療科
公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科