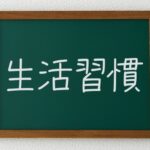高血圧症と脂質異常症は気が付きにくい?定期的な健診が大切!
生活習慣病と言われる高血圧と脂質異常症は命に関わるような危ない病気を引き起こすかもしれません。
本記事では、高血圧症と脂質異常症について詳しく解説します。
現在、高血圧や脂質異常症でお悩みの方はもちろん。
それ以外の方もぜひ参考にしていただき、健康的な生活を送りましょう。
目次
高血圧症について
高血圧症は、その発症の原因から「本態性高血圧」と「二次性高血圧」の二つに分類されます。
そのうち本態性高血圧は、一次性高血圧と呼ぶこともある高血圧で、日々の食生活などが原因になる高血圧です。
逆に二次性高血圧は、原因となる疾患が別にある高血圧を指します。
本態性高血圧(日本人のほとんどがこれ)
日本人の高血圧症のうち、90%~95%は本態性高血圧と言われています。
本態性高血圧は、一次性高血圧ともいわれ、明確な原因が指摘できない高血圧です。
原因がないわけではなく、いろいろな要素が組み合わさって高血圧になっていきます。
この本態性高血圧では特に自覚症状がないことが多く、健診などで指摘されて初めて気づくということも少なくありません。
日本人では食塩の過剰摂取がもっとも大きな原因で、その他に以下などの原因が考えられます。
- 肥満
- 飲酒
- 運動不足
- ストレス
- 遺伝的体質
二次性高血圧
本態性高血圧と異なり、高血圧になった原因を特定できるものを二次性高血圧とよびます。
その原因は以下などに細分化されます。
- 腎実質性
- 腎血管性
- 内分泌性
- 血管性
- 脳・中枢神経性
- 遺伝性
- 薬剤性
自覚症状が乏しい本態性高血圧に比べて、二次性高血圧は高血圧になる原疾患があるため、何かしらの症状が出現する場合があります。
そして、二次性高血圧はその原疾患を治療できれば、高血圧が治癒したり容易にコントロールできるようになったりします。
しかし、実は二次性高血圧であるが、自覚症状などが乏しいため気が付かれず、本態性高血圧として治療をされれている方が多いのも実情です。
本態性高血圧よりも二次性高血圧を疑う状況は、以下などです。
- 若年で発症する高血圧
- 急速に発症した高血圧
- 治療抵抗性の高血圧
- 臓器障害を強く伴う高血圧
- 夜間高血圧
- 低カリウム血症などの電解質異常を伴う高血圧
病院と家庭で測る血圧の基準がある
血圧は常時一定であるものではなく、1日の中でも時間帯や測定する状況で変動があります。
その中でも、病院で測定する病院血圧(診察室血圧)と家庭で測定する家庭血圧は明らかに異なることが多いため、別の基準が設けられています。
その理由には、病院で血圧測定する時は、病院という環境に緊張される方が多く、家庭などのリラックスした状態で測るよりも血圧が高くなることが知られています。
中には、病院で測定したときのみ異常に高血圧になる方もいらっしゃり、白衣高血圧と呼ばれています。
そのため、高血圧の基準とされる値は、家庭血圧が病院血圧よりも低く設定されています。
また、降圧治療の評価のためにも家庭血圧を測定して主治医に報告することが大切です。
病院基準
|
病院における高血圧診断基準 |
上の血圧(収縮期血圧)140mmHg以上 下の血圧(拡張期血圧)90mmHg以上 |
|
Ⅰ度高血圧 |
上の血圧(収縮期血圧)140~159mmHg 下の血圧(拡張期血圧)90~99mmHg |
|
Ⅱ度高血圧 |
上の血圧(収縮期血圧)160~179mmHg 下の血圧(拡張期血圧)100~109mmHg |
|
Ⅲ度高血圧 |
上の血圧(収縮期血圧)180mmHg以上 下の血圧(拡張期血圧)110mmHg以上 |
家庭基準
家庭血圧による高血圧の基準値は、135/85 mmHg以上です。
なれた自宅でリラックスして測られることが多いため、診察室血圧よりも5 mmHg低い基準値となっています。
つまり家庭血圧が高い方は、同じ病院血圧の人と比較して、より重症であると判断ができます。
そして、最近の研究では脳卒中や心筋梗塞などの高血圧に伴う病気の発症を予測する方法として、病院血圧よりも家庭血圧のほうが優れていることが分かってきました。
そのため、診察室血圧と家庭血圧の数値に大きな差がある場合、家庭血圧の数値を優先して高血圧の診断を行うようになっています。
脂質異常症について
血液検査の脂質の値が基準値から外れた状態を、脂質異常症といいます。
脂質の異常には、以下の3種類の異常があります。
- LDLコレステロール(悪玉コレステロール)
- HDLコレステロール(善玉コレステロール)
- トリグリセライド(中性脂肪)
これらそれぞれの脂肪の異常が単独である場合と、複数の異常脂質異常が同時にみられる場合があります。
メタボリックシンドロームの診断基準に用いられる脂質はHDLコレステロール、トリグリセライドであるため、それらが重要だと考える方もいるでしょう。
しかし、LDLコレステロールはそれ単独でも強力に動脈硬化を進行させるため、メタボリックシンドロームの有無に関係なく、LDLコレステロールの値にも注意する必要があります。
以前は高脂血症と呼ばれていましたが、善玉のHDLコレステロールが低い場合も問題があることが判明し、それを高脂血症と呼ぶのは適当でないことなどから、診断名を高脂血症から脂質異常症となりました。
高LDLコレステロール血症
増えすぎると動脈硬化を起こして心筋梗塞や脳梗塞を発症させるもので、俗に言う悪玉コレステロールです。
悪玉と言っても人体で重要な役割も果たしているため数値が通常の範囲であれば全く問題ありませんが、過剰に存在すると余分なLDLコレステロールが血管壁にたまってしまいます。
それは活性酸素の影響で酸化され、さらに蓄積し血管を細くさせ心筋梗塞や狭心症・脳梗塞などの動脈硬化性疾患を誘発させます。
LDLコレステロールの正常範囲は140mg/dl未満です。
140mg/dl以上の場合は高LDLコレステロール血症になります。
低HDLコレステロール血症
余分なコレステロールを回収して動脈硬化を抑える機能を持つものであり、善玉コレステロールとも言われています。
増えすぎたコレステロールが動脈硬化を促進するのとは反対に、動脈硬化を抑制する働きがあるので善玉コレステロールといわれます。
日々の生活の中では、LDLコレステロールを減らしHDLコレステロールを増やすことが、健康的な生活とも言えます。
運動不足や喫煙がHDLコレステロールを下げる原因になると考えられているため、低HDLコレステロール血症で困っている方は注意してみてください。
高トリグリセライド血症
トリグリセライドは中性脂肪と呼ばれ、肉や魚・食用油など食品中の脂質であり、単なる脂肪と認識してもらっても間違いありません。
中性脂肪は人にとっては重要なエネルギー源であり、脂溶性ビタミンや必須脂肪酸の摂取にも不可欠ですが、とりすぎると肥満をまねき、生活習慣病を引き起こします。
血液中の中性脂肪は食事によって深く影響を受け、メタボリックシンドロームの診断基準にも記載があります。
高トリグリセライド血症で悩む方は、日々の食事の中や生活習慣を見直す必要があり、食事では特に脂っこいものを節制する必要があります。
高血圧症と脂質異常症の関係と共通する原因
運動不足
WHOは、運動不足を世界の死亡に対する第4位の危険因子として位置付けています。
また、運動不足は肥満の原因にもなり、肥満が高血圧や脂質異常症の原因となるためです。
日々の健康維持のためには、適切な運動の実施が欠かせず、適切な運動をすることは脳心血管病の発症を予防することができます。
高血圧症においては運動で改善することが知られており、運動療法とも言われます。
運動の頻度は定期的に実施し、1回30分以上、ややきついと感じるくらいの有酸素運動が勧められています。
肥満(血圧とコレステロールの関係)
肥満はただ体重が重いことを指すよりも、過剰な体脂肪がついてしまっていることを指します。
肥満患者では動脈硬化の原因となる内蔵脂肪が過剰なため、血圧が高くなりやすいことがわかってきました。
国民の3~4人に1人が高血圧といわれていますが、肥満の人では2人に1人の割合に増えます。
高血圧の状態が続くと血管の壁の内側に傷がつき、そこに血液中のコレステロールなどがたまって動脈硬化を招き、やがて狭心症や心筋梗塞などの病気を引き起こします。
自覚症状がないため気が付きにくいですが、肥満を改善することは健康に生きるためにとても大事になります。
塩分の摂りすぎ
不健康な食事として高カロリー食や塩分過多による食事が挙げられます。
そのうち、なぜ塩分を過剰に摂取することが不健康とされるかというと、塩分は水を含む性質があるため、過剰に塩分摂取すると体内にナトリウムと水が貯まり、血液の量が増加し血圧が上がると考えられています。
時折塩分過剰になることはさほど問題ありませんが、普段から塩分の食事を続けることは高血圧などの原因になり注意が必要です。
飲酒
アルコール摂取により大きく影響を受ける脂質は、トリグリセライドとHDLコレステロールです。
アルコールをすると肝臓がトリグリセライドを作るため、血液中に漏れる高トリグリセライド血症になることにもあります。
そして肝臓に残ったトリグリセライドは肝臓に溜まり脂肪肝の原因となります。
適量のアルコール摂取はHDLコレステロールの合成・分泌を増やし、分解を低下させる働きがあることも知られており、これが適量の飲酒であれば、血圧を上げずに脳血管障害・冠動脈疾患の発生を低下させると言われている原因です。
ただ、過度なアルコール摂取は肥満や高血圧を引き起こすため脳血管障害・冠動脈疾患の危険因子になるため注意が必要です。
ストレス過多
緊張すると血圧が上がるということは聞いたことがあるかもしれません。
その典型例は、先ほど紹介した白衣高血圧(病院高血圧)です。
つまり過度の緊張やストレスは、血圧の上昇と深い関連があります。
高血圧患者で食事などに気をつかっている人でも、ストレスについては無関心ということが少なくありません。
ストレスが直接高血圧の原因になることもあるため、ストレスが強い環境にさらされ続けるのは避けなければいけません。
血圧をコントロールするためにも自分のストレスや、その解消方法について理解しておくことが大切です。
命にかかわる合併症を引き起こすことも
生活習慣病には高血圧、脂質異常症、糖尿病などいくつかありますが、そのいずれにおいても初期の段階では自覚症状がほとんどありません。
しかし生活習慣は症状がないからといって放置しておくと、気づかないうちに進行し動脈硬化を進行させ血管にダメージを与えていきます。
そして血管が関係する病気はある日突然発症します。特に血管が関与する病気の中でも狭心症や心筋梗塞、脳卒中などは1度の発症で命を落とすことにもつながります。
ここに生活習慣病がサイレントキラーと呼ばれている所以があります。
心筋梗塞などが起こり手遅れになる前に、高血圧・脂質異常症と診断されたら、症状がなくても食事や運動など生活習慣を見直しましょう。
また治療に前向きに取り組み、生活習慣病の予防に努めることが重要です。
関連記事:【生活習慣病の方に知ってほしい】心筋梗塞の症状や前兆について
西春内科在宅クリニックができる対応
西春内科在宅クリニックでは、内科診察・血液検査が可能です。高血圧に対しては家庭血圧・病院血圧の評価や必要時の内服処方を外来で行うことができます。
また脂質異常症に対してはLDLコレステロール値や中性脂肪などの採血検査・評価・投薬治療が可能です。
まとめ
不健康な食事や運動不足、喫煙、アルコール過剰摂取といった生活習慣は、高血圧や脂質異常症の原因になるほか、いずれは心筋梗塞や脳卒中といった重要な病気につながるため注意が必要です。
高血圧や脂質異常症といった生活習慣病はほとんど自覚症状がないため自分で気づかない方も多いですが、予防のためにも日頃からバランス取れた食事、運動、体重のコントロール、お酒の量を減らす、禁煙を心がけることが大切です。
【参考文献】
監修医師: 外科専門医 梅村 将成

資格
外科専門医/腹部救急認定医