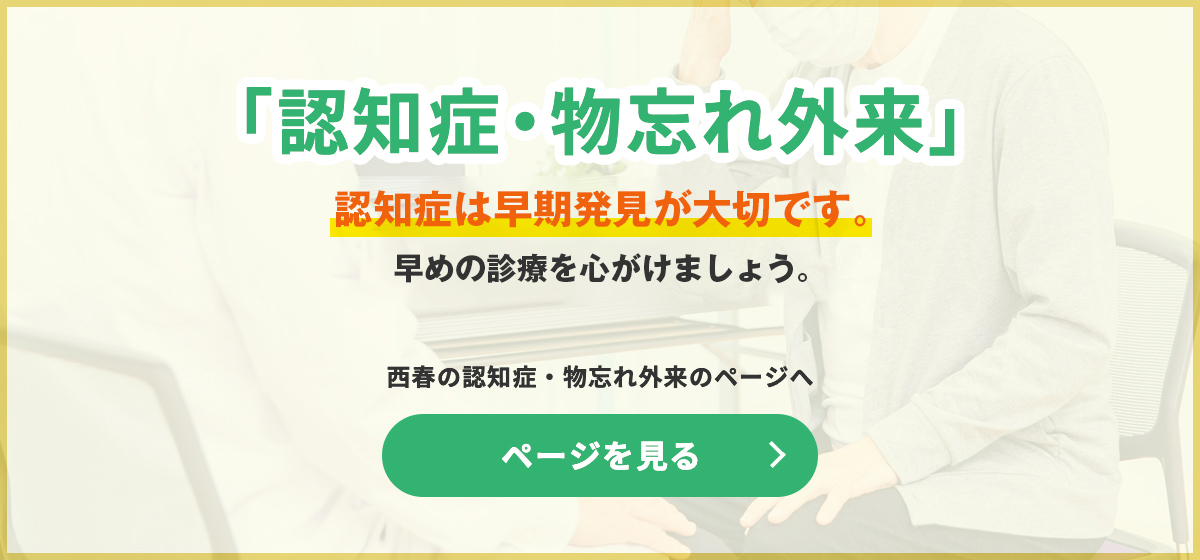認知症における顔つきの特徴と症状や種類について
認知症とは、加齢とともに伴う脳の障害により、これまで出来ていた仕事や社会生活に支障をきたした状態を指します。
年齢とともに増加し、発症原因の違いに様々な症状を生じます。
この記事では認知症の顔つきの特徴についてや症状・初期症状についてをご紹介させて頂きます。
目次
認知症になると顔つきが変わる理由と特徴
認知症によって、物忘れなどの認知機能が低下すると、以前よりも外からの刺激へ反応が乏しくなり、抑うつ傾向になることがあるため、顔つきが変化することがあります。
具体的には、目つきで生気が失ったように眼瞼が下がり、元気がなくなり、全体的に表情が乏しく抑うつ状態になることなることがあります。
以前よりもぼんやりとしている、無表情が多い、悲しそうな暗い表情多いなどに気が付いたら危険信号だと考えてください。
関連記事:認知症が一気に進む原因や知っておきたい予防と対策について
認知症になる原因
認知症は、加齢に伴い、さまざまな原因により脳における神経細胞の働きが低下して起こる認知機能低下一連の状態をいいます。
認知症の原因になりうる病気としては、もっとも頻度の高いもので、アルツハイマー型認知症が挙げられます。
そのほか、代表的な認知症の原因疾患として、以下が挙げられます。
- レビー小体型認知症
- 前頭側頭型認知症
- 血管性認知症
認知症の代表的な4種類について
認知症はそれぞれの病気によって、症状の現れ方が異なり、治療法・対応方法が変わることもありますので、下記で、それぞれの病気について詳しくみていきます。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症は、物忘れを主体とした認知機能障害に加えて、実際には見えないものが見えるという「幻視」をよく認めることがあります。
特徴的な幻視を疑わせる訴えとしては、”地面に虫が這っている”、”知らない人がそこに座っている” などです。
上記症状に加えて、パーキンソン症状に関連した運動の症状(体が固くなり動きにくくなり、手の震え・歩行時に急に止まれないなど)、自律神経障害(起立性低血圧、便秘、尿失禁など)を認めることもあります。
これらの症状により転倒する危険が高くなりますので、十分に歩行や移動には注意する必要があります。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、認知症の原因では最も頻度が高く、患者数の多い病気です。
脳の側頭葉という部分のうち記憶に関わる海馬という部分が初期からが萎縮するのが特徴です。
症状としては、物忘れや記憶障害といった認知機能障害から始まり、徐々に進行していきます。
症状の進行とともに、以下のような周辺症状といわれる症状を認めることがあります。
- 周囲に攻撃的になって暴言や暴力を振るう
- 家に閉じこもって周囲のことに無関心になる
- 実際に見えないものが見える(幻覚)
- お金を取られたと思い込む(ものとられ妄想)
- 睡眠障害
- 食行動異常
- 多動・徘徊
血管性認知症
加齢とともに脳の血管が詰まったり(脳梗塞)、破れたりして出血(脳出血)するリスクが上昇します。
脳血管の障害に伴って、脳の血流が悪くなり血流が不足することで脳の機能が低下することで生じる認知症が血管性認知症です。
血流障害の部位によって臨床症状に差があり、物忘れなどの認知機能障害のほか、手足の震えや麻痺、歩行障害などの運動障害を合併することがあります。
そのほか、意欲の低下や抑うつ、情動失禁といった感情面の症状も認めることもあります。
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉と側頭葉という部分が障害されること、物忘れよりも性格の変化、社会性の欠如、同じことを繰り返していうといった症状が主体として初期から認めます。
そして、他の認知症よりも発症年齢が比較的若いことが多いため、初期症状として物忘れよりも性格の変化をメインとするため、精神疾患などと混同することがしばしばあります。
行動を自分で抑制して調整することが難しいため、判断力、集中力が低下し人格・性格が変化することが特徴です。
また、窃盗、多動、徘徊といった社会性が失われる行動をとることがあります。
側頭葉の機能が低下することにより、言葉を正確にしゃべったり、理解したりする機能が低下しますので、言葉の理解が困難になることもあります。
関連記事:アルツハイマーと認知症の違いは?原因や初期症状、なりやすい人の特徴について
気をつけてほしい認知症の初期症状
高齢化社会で高齢者の人口比率が多くなっている今日では、認知症は誰にとっても起こりうる状態で、他人事ではない時代と考えてください。
ですので、以下などの症状が出てきたら、中核症状である認知機能の障害を考える必要があります。
- 「毎日の出来事を忘れっぽくなってきた」
- 「物を置いた場所を忘れるようになった」
- 「毎日飲んでいる薬などの管理することが苦手になってきた」
また、家族の方で以下のような変化を認められたら、中核症状と環境因子・性格などが相互作用して生じる周辺症状が疑われます。
- 怒りっぽくなった
- 趣味への興味を失って周囲のことに無関心になってきた
- 自分の外見を気にしなくなった
- 徘徊するようになった
- 以前よりも多弁・多動になった(おしゃべりが多くなった)
上記のような症状が現れましたら、認知症の初期症状の可能性がありますので、一度病院受診も検討してみてくださいね。
もし家族や身内が認知症かと疑ったときの対応
認知症は、早期診断して、早期介入により、生活環境を整えて、早期治療を行うことが重要です。
症状が軽度の段階で、適切な治療・生活リズムへの介入をすることにより、認知症の症状を改善できることが期待できます。
ですので、自分自身だけでなく家族、友人など周りの人の方で「もしかして認知症ではないか」と思われる症状に気づいたら、まず、かかりつけの医師または、お住まいの地域の医療機関の「もの忘れ外来」に受診しましょう。
そこで、問診・診察・検査(認知機能検査・血液検査・尿検査・画像検査)で総合的に評価することによって、早期診断・早期治療につながります。
関連記事:物忘れがひどくなる原因は?|認知症との違いや物忘れ対策について
西春内科在宅クリニックができる認知症への対応
当院では、認知症が疑われる患者様の診断・治療に早期から介入して、患者様・ご家族がより良く暮らしていける生活環境を整えることに全力で取り組みたいと考えております。
上記に説明しましたような物忘れや性格の変化を疑われる症状を見ましたら、まずはお気軽にご相談ください。
認知症は、クリニック・病院での治療のみで治すことが難しい病気です。
生活環境を整えて最善のケアをすることが重要となってきます。
当院は、認知症患者様を地域全体で支える体制を構築し、ご家族・介護者様と協力しながら適切なサポートをいたします。
まとめ
繰り返しにはなりますが、認知症は早期診断・早期介入により、生活環境を整えて、早期治療を行うことが重要です。
患者様・ご家族様の気持ちを受け止めて、それぞれの症状・状況を考慮したオーダーメイドの治療・ケアを心がけたいと考えておりますので、気になる方はぜひ一度ご相談くださいね。
参考文献
認知症疾患診療ガイドライン2017 (医学書院)
監修医師: 福井 康大
監修医師: 西春内科・在宅クリニック 院長 島原 立樹

▶︎詳しいプロフィールはこちらを参照してください。
経歴
名古屋市立大学 医学部 医学科 卒業三重県立志摩病院
総合病院水戸協同病院 総合診療科
公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科